家庭菜園で人気のハーブ、バジル。その爽やかな香りは料理を一層引き立ててくれますよね。しかし、「うちのバジル、そろそろ寿命かな?」「何年も収穫できますか?いつまでとれる?」といった疑問を感じたことはありませんか。
バジルの育て方には、収穫量を増やすためのちょっとしたコツがあります。例えば、茎が硬く木質化したらどうするのか、大きくなりすぎたバジルはどうすればいいですか?という悩みや、そもそも種まきからシーズンが終わったらどう片付ければいいのか、という一連の流れを知っておくことが大切です。
また、バジルは庭に植えてはいけないと言われることもありますが、その理由や室内での上手な管理方法、さらには冬越しのテクニックまで、知っておきたいポイントはたくさんあります。この記事では、バジルの寿命を最大限に延ばし、収穫した葉を美味しくいただくためのレシピまで、あなたの疑問を解決する情報を詳しく解説します。
この記事でわかること
- バジルが一年草として扱われる理由と本来の寿命
- 収穫量を増やし寿命を延ばすための具体的な育て方
- 冬越しを成功させ、翌年も楽しむための管理方法
- 収穫したバジルを無駄なく活用するための保存法やレシピ
そもそもバジルの寿命はどのくらい?
- バジルの寿命を左右する育て方の基本
- 何年も収穫できますか?いつまでとれる?
- 寿命が近いサイン?茎が木質化したら
- 大きくなりすぎたバジルはどうすればいいですか?
- 庭に植えてはいけないと言われる理由
バジルの寿命を左右する育て方の基本

ベランダで育てるハーブ
バジルの寿命は、その育て方によって大きく変わります。植物学的には多年草に分類されるバジルですが、原産地である熱帯アジアとは異なり、日本の気候では冬の厳しい寒さに耐えられず枯れてしまうため、園芸上は一年草として扱われるのが一般的です。しかし、適切な環境と手入れを施すことで、単年で終わらせず、収穫期間を長くし、寿命を延ばすことが可能です。
バジルを元気に長く育てるための基本的な三大要素は、「日当たり」「水やり」「風通し」です。まず、バジルは日光を非常に好む植物であり、その生育と香りの強さは日照量に大きく左右されます。
理想的には1日に最低でも5〜6時間は直射日光が当たる、日当たりの良い南向きのベランダや庭で育てましょう。日照不足に陥ると、茎が間延びしてひょろひょろと弱々しく育つ「徒長」という状態になり、葉の色が薄くなるだけでなく、バジル特有の豊かな香り成分の生成も妨げられてしまいます。
次に水やりですが、これはバジルの健康を維持する上で非常にデリケートな管理が求められます。基本は、土の表面が乾いたのを確認してから、鉢底から水が十分に流れ出るまでたっぷりと与えることです。
特に真夏の高温期は水分の蒸発が激しく、朝に水やりをしても夕方には土が乾いてしまうことも珍しくありません。水切れを起こすと葉がしおれてしまうため、こまめなチェックが必要です。
一方で、常に土がジメジメと湿っている状態は、根が酸素不足に陥り腐ってしまう「根腐れ」の最大の原因となります。水のやりすぎは禁物であり、「乾いたらやる」のメリハリが重要です。
そして、見落としがちながら重要なのが風通しです。葉が密に茂りすぎると、株の内部に湿気がこもり、アブラムシやハダニなどの害虫や、うどんこ病といったカビが原因の病気が発生しやすくなります。
これを防ぐためには、定期的に葉を収穫することを兼ねて、混み合った枝を切り取る「剪定」を行い、株全体の風通しを良く保つことが不可欠です。このひと手間が、バジルを病害虫から守り、健康な状態を維持させ、結果的に寿命を延ばすことにつながるのです。
育て方の基本チェックリスト
- 日当たり:南向きの場所で1日5〜6時間以上、日光を確保できているか?
- 水やり:土の表面が乾いてからたっぷりと与え、受け皿の水は捨てているか?
- 風通し:葉が密集していないか?定期的な収穫や剪定で風の通り道を確保しているか?
これらの基本的な育て方を丁寧に守ることが、バジルのポテンシャルを最大限に引き出し、寿命を延ばすための揺るぎない土台となります。
何年も収穫できますか?いつまでとれる?

ベランダで育てるハーブ
「バジルを一度植えたら、何年も収穫し続けられるの?」という疑問は、家庭菜園を楽しむ多くの方が抱くものです。この答えは、栽培環境に大きく依存します。
結論から言うと、日本の一般的な屋外環境(地植えやベランダでの放置栽培)では、残念ながら何年も収穫し続けるのは非常に難しいです。
前述の通り、バジルは熱帯生まれの植物で寒さに極端に弱いため、農林水産省が提供する情報でも、生育適温は20~30℃とされています。
気温が10℃を下回ると成長が鈍化し、5℃以下になると生育がほぼ完全に停止します。そして、霜が一度でも降りてしまうと、細胞が破壊されてしまい、ほぼ確実に枯死してしまいます。(参照:農林水産省「バジルシードの栽培はできますか。」)
このため、春に苗を植えたり種まきをしたりした場合、屋外での収穫期間は主に初夏から晩秋(具体的には6月〜10月頃)までとなります。
特に気温が高く日差しも強い7月〜9月が最も生育旺盛な時期で、適切な管理を行えば、毎週のように新しい葉を収穫することが可能です。
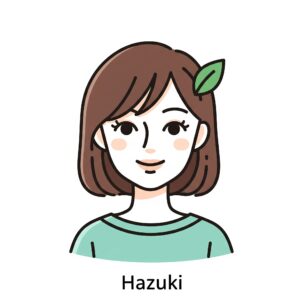
冬場に鉢植えを室内に取り込み、適切な温度と日光を管理すれば、バジルは冬を越し、翌春に気温が上がるとともに再び新しい芽を出し始めます。
これにより、同じ株から2年、3年と収穫を再開することが理論上は可能です。つまり、少しの手間と工夫を惜しまなければ、バジルを一年草として終わらせず、多年草のように何年も収穫を楽しむことも夢ではないのです。
要約すると、屋外での栽培ではその年限り、鉢植えにして冬越し対策を施せば翌年以降も収穫が期待できる、と覚えておくと良いでしょう。
寿命が近いサイン?茎が木質化したら

ベランダで育てるハーブ
バジルを長期間育てていると、株元に近い茎が徐々に茶色く変色し、まるで木の枝のように硬くなってくる現象が見られます。これは「木質化(もくしつか)」と呼ばれる状態で、バジルの株が成熟し、古くなってきたことを示すサインです。
これは病気ではなく、植物が自重を支えるために組織を強化する自然な老化現象ですが、収穫を楽しむ上では寿命が近づいている兆候の一つと捉えることができます。
木質化が始まると、いくつかのデメリットが生じます。最も大きな問題は、木質化した硬い部分からは、新しい芽や葉がほとんど出てこなくなることです。成長のエネルギーが若い上部の枝に集中するため、株全体の収穫量が徐々に減少し始めます。
また、葉の風味にも影響が出ることがあり、若い茎から収穫した柔らかく香り高い葉に比べて、やや風味が落ちるとも言われています。
もし、あなたのバジルに木質化のサインが見られたら、諦めるのはまだ早いです。いくつかの対処法によって、株を若返らせたり、次の世代に命を繋いだりすることが可能です。
木質化への対処法
- 切り戻し剪定による若返り
木質化が株全体に及んでいなければ、まだ緑色で柔らかい若い枝がたくさん残っているはずです。この場合、木質化した部分の少し上で思い切って切り戻し剪定を行うと、残された若い節から新しい芽の発生が促されます。これにより株がリフレッシュされ、再び柔らかい葉を収穫できるようになる可能性があります。 - 挿し木による株の更新
最も確実な方法が「挿し木」です。木質化していない元気な若い先端の茎を10cmほどの長さで切り取ります。下のほうの葉を取り除き、水の入ったコップや瓶に挿しておくと、数日から1週間ほどで白い根が生えてきます。この根が十分に伸びたら、新しい土に植え付ければ、遺伝的に全く同じ性質を持つ新しい株(クローン)の完成です。親株の寿命が近づいていても、この方法で株を無限に更新し、収穫を続けることができます。
木質化は病気ではありませんが、放置すれば収穫の終わりが近づく「老化」のサインです。初期段階で見つけたら、早めに「切り戻し」や「挿し木」で対処することで、美味しいバジルをより長く楽しむことができます。
木質化が株の大部分に進行し、新しい葉の出方が極端に少なくなってしまった場合は、株の寿命と判断し、挿し木で次の世代を育てることに切り替えるのが賢明です。
大きくなりすぎたバジルはどうすればいいですか?

ベランダで育てるハーブ
バジルは生育旺盛なハーブで、特に日当たりと気温に恵まれた夏場には、驚くほどのスピードで大きく成長します。一見、元気に育っている証拠で喜ばしいことのように思えますが、大きくなりすぎたバジルをそのまま放置すると、かえって株の寿命を縮める原因になりかねません。
具体的には、以下のような問題が発生します。
大きくなりすぎたバジルの問題点
- 蒸れによる病害虫の発生:葉や枝が密集しすぎることで内部の風通しが悪化し、湿気がこもります。これは、うどんこ病などのカビや、アブラムシ・ハダニといった害虫の温床となります。
- 下葉の枯れ:上部の葉が傘のようになり、株元の葉に日光が当たらなくなります。光合成ができなくなった下の葉は黄色く変色し、やがて枯れ落ちてしまいます。
- 開花と葉の硬化:株が成熟しすぎると、子孫を残そうとして花芽(かすい)をつけ始めます。花が咲くと栄養がそちらに集中し、葉が硬くなり香りも落ちてしまいます。
このような状態を防ぎ、株を健康に保つためには、大きくなりすぎたと感じたら、定期的な「収穫」を兼ねた大胆な「剪定」で管理することが不可欠です。特に茂りすぎている場合は、思い切って株全体の高さが半分から3分の1程度になるまで切り戻す「切り戻し剪定」を行いましょう。
切り戻し剪定の重要なコツ
剪定で枝を切る位置は、必ず葉の付け根のすぐ上です。葉の付け根には「脇芽」と呼ばれる、これから新しい枝になるための芽が左右に控えています。この脇芽を必ず残すようにして、その数ミリ上で切ることが非常に重要です。この作業により、切った箇所から新たに2本の茎が伸びて枝数が増え、結果的に収穫量が倍増していきます。
剪定によって一度に大量の葉を収穫した場合は、すぐに使い切れない分をジェノベーゼソースに加工したり、乾燥させてドライバジルにしたりと、長期保存できる形に活用するのがおすすめです。また、切り取った元気な茎は、前述の通り「挿し木」に利用すれば新しい株を増やすこともできます。

庭に植えてはいけないと言われる理由

ベランダで育てるハーブ
「バジルはミントと同様に、庭に直接植えてはいけない」というアドバイスを園芸の情報サイトなどで見かけることがあります。これはいくつかの明確な理由に基づいており、絶対にダメというわけではありませんが、プランター栽培に比べて注意すべき点が多いのは事実です。
理由1:連作障害のリスク
最も大きな理由が「連作障害」です。バジルはシソ科の植物に分類されます。同じ科の植物を同じ土壌で毎年続けて栽培すると、土の中の特定の栄養素だけが過剰に消費されてバランスが崩れたり、その植物を好む特定の病原菌や害虫が土壌中に蓄積したりして、次第に生育が悪くなる現象が起こります。これを連作障害と呼びます。一度庭にバジルを植えると、翌年以降、同じ場所にはバジルはもちろん、同じシソ科の植物(シソ、ミント、ローズマリー、セージなど)を植えることが難しくなります。
主なシソ科のハーブ・野菜
| 種類 | 代表的な植物 |
|---|---|
| ハーブ | バジル、ミント、シソ(大葉)、ローズマリー、セージ、タイム、オレガノ、レモンバームなど |
| その他 | エゴマ、シソの実など |
これらの植物を同じ場所で続けて栽培するのは避けましょう。
理由2:病害虫の管理の難しさ
庭の土壌には、プランターの清潔な培養土とは異なり、多種多様な微生物や昆虫が生息しています。そのため、地植えはプランター栽培に比べて病害虫に遭遇するリスクが高まります。
特に、風通しが悪くなるとアブラムシやハダニ、うどんこ病などが発生しやすくなります。一度庭で病害虫が広がってしまうと、周囲の他の植物にも影響を及ぼす可能性があり、その駆除や管理が大変になる場合があります。
理由3:予期せぬ繁殖
バジルはミントのように地下茎で爆発的に増えることはありませんが、花が咲いた後にできる種が地面にこぼれ、翌年、思わぬ場所からたくさんの芽を出すこと(こぼれ種)があります。手入れの行き届いた庭なら問題ありませんが、放置すると雑草のように広がってしまう可能性もゼロではありません。
地植えを選ぶ場合の必須条件
もしどうしても庭に植えたい場合は、過去2〜3年はシソ科の植物を植えていない場所を選び、腐葉土や堆肥をすき込んで水はけの良い土壌に改良することが不可欠です。また、株間を最低30cmは確保し、成長しても風通しが悪くならないように配慮しましょう。
これらの理由から、特に限られたスペースで栽培する家庭菜園や初心者の方には、土の入れ替えや移動が容易で、連作障害や病害虫の管理がしやすいプランターや鉢での栽培が強く推奨されています。「庭に植えてはいけない」というのは、こうしたリスクを未然に防ぐための、経験に基づいた園芸の知恵と言えるでしょう。
バジル寿命を延ばすための栽培テクニック
- 種まきから始める長期収穫計画
- 室内で管理して寿命を延ばすコツ
- バジルの冬越しに挑戦する方法
- 大量収穫バジルのおすすめレシピ
種まきから始める長期収穫計画

ベランダで育てるハーブ
バジルの寿命を最大限に活用し、シーズンを通して途切れることなく新鮮な葉を収穫し続けるためには、栽培のスタート地点である「種まき」の段階から計画的に行うことが非常に有効です。
市販の苗から育てる手軽さも魅力ですが、種から育てることでコストを大幅に抑えつつ、収穫時期を自在にコントロールできるという大きなメリットがあります。
収穫をリレーする「ずらしまき」
最も効果的なテクニックが、一度に全ての種をまくのではなく、2〜3週間おきに時期をずらして何回かに分けて種まきをする「ずらしまき(リレー栽培)」です。例えば、5月上旬に第1弾、5月下旬に第2弾、6月中旬に第3弾といった具合に計画します。
この方法の最大の利点は、収穫のピークを分散できることです。第1弾の株が夏の盛りに収穫の最盛期を迎え、少し疲れてきたり、茎が木質化し始めたりする頃に、第2弾の若い株がフレッシュな状態で収穫期を迎えます。これにより、常に柔らかく香りの良い最良の状態の葉を、初夏から晩秋まで途切れることなく収穫し続けることが可能になります。
種まきを成功させるための基本的な方法とポイントを以下にまとめます。
| 項目 | 内容とポイント |
|---|---|
| 種まき適期 | 発芽には20℃以上の地温が必要なため、屋外では八重桜が散る頃の4月下旬〜6月が目安です。早まきする場合は室内で保温します。 |
| 用土 | 雑菌の少ない市販の種まき用土か、新しい野菜用培養土を使用するのが最も安全で確実です。 |
| まき方 | セルトレイや育苗ポットに土を入れ、深さ5mm程度のまき穴を指で軽くつけ、そこに2〜3粒ずつ種が重ならないようにまきます。 |
| 覆土(土をかぶせる) | バジルの種は発芽に光を必要とする「好光性種子」です。そのため、土はごく薄く、種が隠れるか隠れないか程度にかけるのが最大のポイントです。深く植えると発芽率が著しく低下します。 |
| 水やり | 種が流れてしまわないよう、霧吹きを使用するか、ジョウロのハス口を上に向けて山なりの優しい水流で水やりをします。発芽するまでは、土の表面を決して乾かさないように管理します。 |
発芽後、本葉が4〜5枚に育ったら、最も元気の良いものを1本だけ残して残りはハサミで根元から切り取り「間引き」をします。この計画的な種まきによって、単一の株の寿命に依存するのではなく、複数の若い株で収穫をリレーさせ、シーズン全体での収穫量と品質を最大化することができるのです。
室内で管理して寿命を延ばすコツ

ベランダで育てるハーブ
屋外では一年草として扱われるバジルですが、秋の終わりに鉢植えを室内に取り込むことで、その寿命を延ばし、冬の間も少量ながらフレッシュな葉を収穫し続けることが可能です。ただし、室内での管理は屋外とは環境が大きく異なるため、成功させるにはいくつかの特別なコツが必要です。
置き場所:光の確保が最優先
室内管理で最も重要な要素は、十分な日光を確保することです。ガラス越しであっても、一日の中で最も長く直射日光が当たる南向きの窓辺などが理想的な場所です。
バジルは光が不足すると、葉の色が薄くなったり、特徴的な香りが弱くなったりするだけでなく、病気への抵抗力も低下してしまいます。
もし適切な場所がない場合は、近年価格も手頃になってきた植物育成用のLEDライトを補助的に使用するのも非常に有効な手段です。
温度管理:寒さから守る
バジルは寒さに非常に弱いため、最低でも室温が10℃以上、できれば15℃程度を保てる環境が望ましいです。特に夜間は窓辺の温度が急激に下がることがあるため、冷え込む夜は窓から少し離れた部屋の中央に鉢を移動させたり、段ボールで窓際を覆ったりするなどの工夫で冷気から守ってあげましょう。
また、エアコンなどの暖房器具の温風が直接当たる場所は、極度に乾燥してしまうため絶対に避けてください。
水やり:過湿は禁物
室内では屋外に比べて空気の流れが少なく、土の乾きが格段に遅くなります。また、冬場はバジルの成長も緩やかになるため、屋外と同じ感覚で水やりを続けると、ほぼ間違いなく根腐れを起こしてしまいます。
水やりのタイミングは、土の表面が完全に乾いてから、さらに1〜2日待ってから与えるくらいでちょうど良いでしょう。指で土を触ってみて、湿り気を感じないことを確認する習慣をつけることが大切です。受け皿に溜まった水は、根腐れの原因となるため、必ず毎回捨ててください。
害虫対策:葉水で予防
暖房で乾燥しがちな冬の室内は、ハダニやアブラムシといった害虫にとっては非常に快適な環境です。これらの害虫は植物の汁を吸って株を弱らせるため、早期発見と予防が重要です。
対策として、定期的に霧吹きで葉の表と裏に水を吹きかける「葉水」を行うと、湿度を保ち、害虫の付着を防ぐ効果があります。もし害虫を見つけたら、数が少ないうちに濡らしたティッシュペーパーなどで優しく拭き取って駆除しましょう。
ポイント
冬の間、バジルは休眠に近い状態になるため、肥料は基本的に必要ありません。もし与える場合は、通常の倍以上に薄めた液体肥料を月に1回程度にとどめ、成長を無理に促さないようにします。春になり、気温が上がって再び成長が活発になってきたら、徐々に通常の肥料管理に戻していきます。
これらのコツを丁寧に実践すれば、バジルの株を健康な状態で冬越しさせ、翌年の春に再び元気な姿で収穫を再開させることが可能です。
バジルの冬越しに挑戦する方法

ベランダで育てるハーブ
前述の通り、バジルは鉢植えであれば室内での冬越しが可能です。単に室内に取り込むだけでなく、適切な準備を行うことで成功率が格段に上がります。
ここでは、秋から冬にかけて、具体的にどのような手順で冬越しの準備を進めればよいかを、ステップバイステップで詳しく解説します。
Step1:株の準備と剪定(10月頃)
まず、冬越しさせたい株を選びます。病害虫の被害がなく、葉の色が濃く元気な株を選びましょう。地植えで育てている場合は、根をできるだけ傷つけないように、株周りの土を大きく掘り上げて鉢に植え替えます。
このとき、根鉢の大きさに見合った鉢を選ぶことが大切です。最初からプランターや鉢で育てている場合は、植え替えの必要はありません。
次に、室内に取り込む前に、株の負担を減らし、病害虫を持ち込まないために思い切った切り戻し剪定を行います。全体の高さが現在の3分の1から半分程度になるように、各枝をバッサリと切り詰めます。
この作業には、枯れた葉や色が変わった枝、弱々しい枝を完全に取り除く工程も含まれます。これにより、株は冬を越すためのエネルギーを無駄遣いすることなく、休眠状態に入りやすくなります。
Step2:室内に取り込む最適なタイミング
バジルを室内に移動させるタイミングの見極めは非常に重要です。天気予報をこまめにチェックし、夜間の最低気温が15℃を下回る日が多くなってきたら、それが取り込みのサインです。ぐずぐずしていると、ある朝突然霜が降り、一晩で致命的なダメージを受けてしまう可能性があります。
「まだ大丈夫だろう」と油断せず、早め早めの行動を心がけましょう。一般的に、地域にもよりますが10月下旬から11月上旬が目安となります。
Step3:室内での具体的な管理方法
室内に取り込んだ後の管理方法は、「室内で管理して寿命を延ばすコツ」のセクションで解説した通りです。日当たりの良い窓辺に置き、水やりは土の乾燥を確認してから控えめに行い、暖房の風が直接当たらないように注意深く見守ります。冬の間はほとんど成長しないかもしれませんが、茎が緑色を保っていれば生きています。
注意ポイント
冬越しに成功した株は、春になって気温が20℃を超える日が増えてくると、 dormant bud(休眠芽)から再び新しい葉を展開し始めます。冬を越した株は茎が木質化して丈夫になっているため、春からの成長スピードは非常に速いですよ。
省スペースな「挿し木」での冬越し
「大きな鉢を冬の間、室内に置くスペースがない」という方も多いでしょう。その場合は、秋に最も元気の良い枝を数本選んで切り取り、「挿し木」で小さな苗を作って冬越しさせるという賢い方法があります。
10cmほどに切った枝を水に挿しておくと簡単に発根するので、それを小さな育苗ポットに植え付けます。これなら窓辺のわずかなスペースでも管理でき、春にはたくさんの新しい苗として畑やプランターに植え付けることが可能です。
冬越しは少し手間がかかる作業ですが、成功すれば翌年の苗を購入する手間とコストを省けるだけでなく、大切に育てた株との付き合いを一年長く楽しむことができます。ぜひ一度、挑戦してみてはいかがでしょうか。
大量収穫バジルのおすすめレシピ

ベランダで育てるハーブ
摘心や切り戻し剪定を行うと、一度にたくさんのバジルが手に入ります。サラダやパスタのトッピングだけでは使い切れないほどの量を収穫できたとき、その豊かな香りを無駄なく、そして長く楽しむための保存も兼ねたレシピを知っておくと非常に便利です。ここでは、大量のバジルを美味しく消費するためのおすすめレシピをいくつかご紹介します。
王道にして最強の保存食!ジェノベーゼソース(バジルソース)
大量消費レシピの代表格といえば、やはりジェノベーゼソースです。フードプロセッサーやミキサーがあれば、驚くほど簡単に本格的なソースを作ることができます。
基本的な材料と作り方
材料:バジルの葉(たっぷりと)、松の実(なければクルミやカシューナッツでも可)、パルメザンチーズ(粉チーズ)、ニンニク、上質なエクストラバージンオリーブオイル、塩。
作り方:全ての材料をフードプロセッサーに入れ、なめらかなペースト状になるまで攪拌するだけです。松の実を軽く炒っておくと香ばしさがアップします。バジルの葉は変色しやすいため、手早く作業するのがポイントです。
完成したソースは、パスタはもちろん、鶏肉や白身魚のソテー、茹でたジャガイモやインゲンと和えるなど、万能調味料として大活躍します。
清潔な瓶に入れて表面をオリーブオイルでコーティングすれば、冷蔵庫で1〜2週間は保存可能です。さらに、製氷皿でキューブ状に小分けして冷凍すれば、必要な分だけ使えて数ヶ月間の長期保存もできます。
香りをオイルやビネガーに閉じ込める
- バジルオイル:清潔な保存瓶に洗って水気をよく拭き取ったバジルの葉を詰め、オリーブオイルをひたひたに注ぎます。冷蔵庫で1週間ほど置けば、バジルの爽やかな香りが移ったフレーバーオイルが完成。サラダドレッシングやパンにつけて楽しめます。
- バジルビネガー:基本的な作り方はオイルと同じで、オイルの代わりに白ワインビネガーやリンゴ酢を使います。マリネ液やピクルス液のベースとして最適です。
エスニック料理で楽しむ
ガパオライス(鶏肉のバジル炒めご飯):タイ料理の定番ガパオライスも、バジルを大量に消費できる嬉しいメニューです。鶏ひき肉やパプリカなどの野菜をナンプラー、オイスターソース、砂糖などで炒め、火を止める直前に、ひとつかみ分のバジルの葉をたっぷりと加えてさっと混ぜ合わせます。加熱しすぎないことで、バジルの鮮烈な香りが引き立ちます。
メモ
最も手軽な長期保存方法は、乾燥させてドライバジルにすることです。収穫した枝を束にして、風通しの良い日陰に逆さに吊るしておくだけで、1〜2週間でパリパリに乾燥します。手で揉んで細かくし、密閉容器に入れておけば、一年中自家製ドライハーブとして利用できます。
新鮮なうちに使い切れない場合は、こうした保存の効くレシピを上手に活用して、丹精込めて育てたバジルの恵みを余すところなく楽しんでください。
よくある質問
バジルの茎が木のように茶色く硬くなってきました。これは病気ですか?
それは「木質化(もくしつか)」という現象で、病気ではありません。
株が成長して古くなってきた自然な老化のサインです。
ただし、木質化した部分からは新しい葉が出にくくなるため、収穫量が減る原因になります。
元気なうちに緑色の若い茎を「挿し木」にして、株を更新するのがおすすめです。
バジルを冬越しさせれば、本当に何年も収穫できるのでしょうか?
はい、可能です。
鉢植えのバジルを秋に室内に取り込み、10℃以上の温度と日光を確保すれば冬を越すことができます。
成功すれば翌春には再び芽吹き、同じ株から収穫を再開できます。
ただし、年々株は老化し木質化も進むため、数年ごとに挿し木で新しい株に更新していくのが、品質を保つ上でおすすめです。
バジルの花が咲いてしまいました。どうすればいいですか?
バジルの花が咲くと、栄養が花や種を作る方に使われてしまい、葉が硬くなったり香りが落ちたりする原因になります。
美味しく葉を収穫し続けたい場合は、花穂(かすい)を見つけたら、すぐに付け根から摘み取ってください。
こまめに花穂を摘むことで、株の寿命を延ばし、長く収穫を楽しむことができます。
収穫するときは、どの葉から摘めば良いのでしょうか?
特定の葉を一枚ずつ摘むよりも、茎の先端を剪定するように収穫するのがおすすめです。
一番上の大きな葉のすぐ下にある、小さな脇芽が2つ出ている節の「上」で茎をカットします。
これにより、脇芽が成長して枝が2本に分かれ、枝数が増えて収穫量もアップします。
これを「摘心(てきしん)」と呼び、バジルを長くたくさん収穫するための重要なテクニックです。
シーズンが終わった後のバジル寿命と来年への準備を総括
- バジルの寿命は熱帯性の性質に起因し、日本の冬の寒さでは屋外での越冬が困難なため一年草として扱われるのが一般的
- 適切な育て方(日当たり・水やり・風通しの確保)を実践すれば、一つの株から初夏から晩秋まで長期間にわたり収穫が可能
- 収穫期間を最大限に延ばすには、花を咲かせないための定期的な摘心(剪定)が不可欠
- 茎が茶色く硬くなる木質化は株の老化サインであり、収穫量や風味の低下につながるため、挿し木による株の更新が推奨される
- 大きくなりすぎた場合は、脇芽の上で切り戻し剪定を行うことで、枝数が増え収穫量アップにつながる
- 庭への地植えはシソ科植物の連作障害を引き起こすリスクがあるため、手軽に土を管理できるプランター栽培が推奨される
- 種まきの時期を数週間ずつずらす「ずらしまき」を行うことで、常に若い株から高品質な葉を収穫し続けることができる
- 鉢植えのバジルは、最低気温が15℃を下回る前に剪定して室内に取り込むことで冬越しが可能
- 冬越し中は、日当たりの良い窓辺で10℃以上を保ち、水やりを控えめにすることが成功のコツ
- 冬越しに成功した株は翌春に再び成長を始め、より丈夫な株として収穫を再開できる
- 大きな鉢を置くスペースがない場合は、秋に元気な枝で「挿し木」苗を作り、小さなポットで冬越しさせる方法も有効
- 剪定などで大量に収穫した葉は、ジェノベーゼソースやバジルオイルに加工したり、冷凍保存したりすることで長期的に楽しめる
- シーズンが終わり霜が降りて枯れてしまった株は、根から引き抜き片付ける
- 来年の栽培に備え、一部の花を咲かせて種を採取(採種)し、乾燥させて冷暗所で保存しておくことができる
- 来年も同じプランターで栽培する場合は、連作障害を避けるために必ず新しい培養土に入れ替えることが望ましい


