ベランダで手軽に始められるバジルの育て方を探しているけれど、バジルを摘心しないとどうなるか気になりませんか?摘心のタイミングや、どこを切ればいいのか分からず失敗するのが怖い、という方も多いでしょう。
そもそも摘心は何回くらいすればいいですか?という疑問や、茎が伸びすぎたらどうすればいいですか?といった悩みもつきものです。
この記事では、摘心に関する基本的な知識から、ホーリーバジルの摘心との違い、水耕栽培や挿し木での増やし方、そして収穫終わりのサインまで、あなたの疑問を総合的に解消します。
この記事でわかること
- バジルを摘心しない場合のメリットとデメリット
- 正しい摘心のタイミングと具体的な方法
- 茎が伸びすぎた際の剪定と活用術
- 収穫量を最大化するための管理のコツ
バジルを摘心しない育て方の基本

ベランダで育てるハーブ
- 初心者向けのバジルの育て方
- 茎が伸びすぎたらどうすればいいですか?
- バジルの収穫終わりの見極め方
- 収穫ついでに挿し木で増やすコツ
- 水耕栽培でバジルを手軽に育てる
初心者向けのバジルの育て方

ベランダで育てるハーブ
バジルは、家庭菜園が初めての方でも気軽に挑戦でき、その爽やかな香りと料理への汎用性から絶大な人気を誇るハーブです。美味しいバジルをたくさん、そして長く収穫するためには、いくつかの基本的なポイントを押さえることが成功への鍵となります。
最重要ポイント:日当たり・風通し・水やり
最も重要なのは、日当たりと風通しの良い場所で管理することです。バジルは日光をエネルギー源として香り成分を作り出すため、日照時間が不足すると葉の色が薄くなったり、香りが弱くなったりします。
理想は、一日に最低でも5〜6時間日光が当たる場所です。ただし、日本の真夏の強烈な西日は葉焼けを引き起こす可能性があるため、ベランダであれば建物の東側や南側に置き、午前中の柔らかな光をたっぷり浴びさせてあげるのがおすすめです。
水やりは、バジル栽培の成否を分ける大切な作業です。基本は「土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与える」ことです。
特に気温が高い夏場は乾燥が早く、朝に水やりをしても夕方には土が乾いていることも珍しくありません。水切れを起こすと葉がしおれてしまうため、こまめに土の状態をチェックしましょう。
一方で、常に土が湿っている状態は、根が呼吸できなくなる「根腐れ」の最大の原因です。水のやりすぎにも十分注意し、土の湿り具合を確認する習慣をつけることが求められます。
バジル栽培の基本セットと選び方
土壌:初心者の方は、最初から肥料成分がバランス良く配合されている市販の「ハーブ用培養土」や「野菜用培養土」を使用するのが最も手軽で確実です。自分で土を作る場合は、「赤玉土6:腐葉土3:バーミキュライト1」などの配合に、緩効性の化成肥料を少量混ぜ込むと良いでしょう。
プランター:バジルは根を広く張るため、窮屈な容器では十分に成長できません。少なくとも直径・深さともに15cm以上のプランターを選ぶことが推奨されます。素材は、通気性に優れるテラコッタ(素焼き)鉢が理想ですが、軽量で扱いやすいプラスチック製でも問題ありません。
肥料:元肥(もとごえ)入りの培養土を使っていれば、植え付けから1ヶ月程度は追肥の必要はありません。その後は、葉の色が薄くなったり、成長が鈍くなったりしたら追肥のサインです。2週間に1回程度の液体肥料か、1ヶ月に1回程度の緩効性化成肥料を与えると、生育が安定します。(参考:サカタのタネ「スイートバジル」栽培方法)
これらの基本を押さえれば、バジルは驚くほど元気に育ってくれます。まずは栽培環境を整え、日々の小さな変化を楽しみながら、バジルとの生活をスタートさせてみましょう。
茎が伸びすぎたらどうすればいいですか?

ベランダで育てるハーブ
バジルを育てていると、特に摘心をしない場合や日照不足の環境下で、茎が間延びしてひょろひょろと上へ伸びすぎてしまうことがあります。これは「徒長(とちょう)」と呼ばれる現象で、見た目のバランスが悪いだけでなく、株が軟弱になり、病気や害虫への抵抗力が弱まる原因にもなります。
茎が伸びすぎたと感じた場合の最も効果的な対処法は、「切り戻し剪定」です。これは、伸びすぎた茎を思い切ってカットすることで、株全体の形をコンパクトに整え、同時に下部の節から新たな脇芽の発生を促す重要な作業です。
具体的には、株全体の高さの半分から3分の1程度の位置を目安に、節(葉が出ている付け根)の1cmほど上を清潔なハサミで切り取ります。このとき、それぞれの枝に必ず数枚の葉を残しておくのがポイントです。葉がない状態で切り詰めすぎると、光合成ができずに株が弱り、最悪の場合枯れてしまうため注意が必要です。
切り戻し剪定の注意点とアフターケア
一度に大量の枝葉を切り落とすことは、植物にとって大きなストレスとなります。全体のバランスを見ながら大胆に、しかしやりすぎないように剪定しましょう。剪定後は、株が新しい芽を出すために多くのエネルギーを消費します。そのため、剪定から1週間後くらいに、通常の規定より少し薄めた液体肥料を与えて回復をサポートしてあげると、その後の生育が格段に良くなります。
切り戻し剪定は、単に樹形を整えるだけでなく、株内部の風通しを劇的に改善します。これにより、湿気がこもるのを防ぎ、カビなどが原因の病気や、ハダニなどの害虫の発生を抑制する効果も期待できます。カットした大量の茎葉は、新鮮なうちに料理に使ったり、乾燥させてドライバジルにしたり、後述する「挿し木」に活用したりと、無駄なく楽しむことができます。
バジルの収穫終わりの見極め方

ベランダで育てるハーブ
バジルはインドなどの熱帯地方が原産の植物で、暑さには非常に強い一方、寒さには極端に弱い性質を持っています。そのため、日本の気候では屋外での冬越しは難しく、基本的には春に植えて秋に収穫を終える一年草として扱われます。
収穫シーズンの終わりを見極める最も重要な指標は「気温」です。バジルの生育適温は20℃〜30℃とされていますが、秋が深まり、夜間の最低気温が15℃を下回る日が続くと、成長は著しく鈍化します。そして、気温が10℃に近づくと葉が黒ずみ始め、霜が一度でも降りてしまうと、細胞が破壊されて株全体が一晩で枯れてしまいます。
天気予報をこまめにチェックし、お住まいの地域で霜の予報が出たら、それが収穫完了の最終デッドラインと考えましょう。気象庁のウェブサイトでは、過去の気象データから「霜の初日」の平年値などを確認することもできます。(参照:気象庁 過去の気象データ検索)
気温以外にも、以下のような株の変化も収穫終わりのサインです。
-
-
- 葉質の変化:葉全体がゴワゴワと硬くなり、特有の柔らかさが失われる。
- 香りの低下:葉をこすっても、最盛期のような強い香りがしなくなる。
-
成長の停止
-
- :新しい芽がほとんど出てこなくなり、株全体の活力が失われる。 -
開花と結実
- :花が咲き終わり、たくさんの種(タネ)ができ始めると、株は子孫を残すことにエネルギーを集中させるため、葉の成長は止まります。
種の採取と来シーズンへの準備
来年も同じバジルを育てたい場合、種を採取しておく楽しみがあります。花が咲き終わって茶色く枯れた花穂を切り取り、数日間、風通しの良い場所でさらに乾燥させます。完全に乾いたら、紙袋などの中で花穂を優しく揉むと、中からゴマのような黒い小さな種がたくさん出てきます。この種を茶こしなどでゴミと選り分け、封筒などに入れて冷暗所で春まで保管しましょう。
収穫シーズンが終わる前に、残っている葉をすべて収穫し、大量消費できるジェノベーゼソースを作ったり、洗浄して水気をよく拭き取ってから冷凍保存したりと、最後の恵みを存分に活用してください。
収穫ついでに挿し木で増やすコツ

ベランダで育てるハーブ
バジルはその旺盛な生命力を活かして、摘心や剪定でカットした茎から新しい株を簡単に増やすことができます。この方法を「挿し木(さしき)」と呼び、コストをかけずに栽培規模を広げられるため、ぜひマスターしたいテクニックです。
挿し木を成功させるための最初のステップは、「挿し穂(さしほ)」となる健康な茎を選ぶことです。まだ花が咲いておらず、適度に硬さのある元気な茎の先端を10〜15cmほどの長さでカットします。
そして、根を出すことにエネルギーを集中させるため、先端についている若く元気な葉を2〜4枚だけ残し、それより下の葉はすべて付け根から取り除きます。さらに、残した葉が大きい場合は、葉からの水分の蒸散を抑えるために、ハサミで半分ほどの大きさにカットしておくと成功率が上がります。
挿し木には主に「水挿し」と「土挿し」の2つの方法があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。
| 方法 | 手順とコツ | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 水挿し | コップや空き瓶に水を入れ、用意した挿し穂を挿しておきます。毎日新鮮な水に交換するのが腐敗を防ぐ最大のポイントです。直射日光の当たらない明るい場所に置きましょう。 | 発根する様子が目で見て確認できるため、初心者でも管理がしやすく、失敗が少ないです。 | 発根後に土へ植え替える作業が必要です。水中の環境に慣れた根が土に馴染むまで少し時間がかかる場合があります。 |
| 土挿し | 湿らせた清潔な土(肥料分のない赤玉土小粒や挿し木・種まき用の土が最適)に、挿し穂を3〜5cmほどの深さで挿します。土が乾燥しないよう、霧吹きで湿り気を保ちます。 | 発根すればそのまま鉢上げして育てられるため、植え替えの手間が省けます。 | 発根したかどうかが目視で確認できず、水やり管理が水挿しに比べて少し難しいです。 |
どちらの方法でも、順調にいけば1〜2週間ほどで切り口や節から白い根が伸びてきます。根が数cmの長さにまで成長したら、新しい鉢に培養土で植え付け、新しい株として育て始めることができます。根がしっかりと土に張るまでは、半日陰で優しく管理してあげることが、その後の順調な成長につながります。
水耕栽培でバジルを手軽に育てる

ベランダで育てるハーブ
「ベランダに土を持ち込みたくない」「キッチンで使う分だけ清潔に育てたい」といったニーズに応えるのが、水耕栽培です。土を一切使わず、水と液体肥料だけで植物を育てるこの方法は、室内で手軽に家庭菜園を楽しみたい方に最適な選択肢と言えます。
最もシンプルで始めやすいのは、500mlのペットボトルを利用した方法です。
- ペットボトルを上から3分の1程度の位置でカットします。
- 飲み口部分を逆さにして、下部のパーツにはめ込みます。
- 飲み口部分に、水を含ませた台所用スポンジやメラミンスポンジを詰め、そこにバジルの種を蒔くか、挿し穂を挿して固定します。
- 下部の容器には、規定の倍率に薄めた水耕栽培用の液体肥料を入れ、スポンジの下端が常に液肥に浸る状態を保ちます。
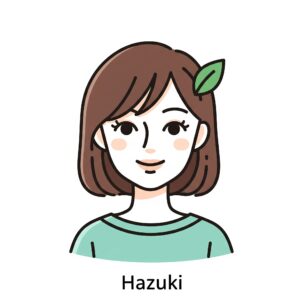
もちろん、市販されている専用の水耕栽培キットを利用するのも良い方法です。特に、日照条件が悪い室内での栽培には、植物育成用のLEDライトがセットになったキットが非常に有効です。光の量や時間をコントロールできるため、天候に左右されずに安定した生育が期待できます。
ただし、水耕栽培には注意点もあります。土壌と違い、水は酸素を保持する力が弱いため、根が酸欠になりやすいのです。また、水温が上がると雑菌が繁殖しやすくなり、根腐れの原因となります。これを防ぐためには、定期的な水の全交換(夏場は3日に1回、冬場でも週に1回が目安)を徹底し、容器を常に清潔に保つことが、水耕栽培を成功させるための最も重要なポイントです。
バジルを摘心しないリスクと正しい摘心

ベランダで育てるハーブ
- 摘心のタイミングはいつが最適?
- バジルの摘心はどこを切るべきか
- 摘心は何回くらいすればいいですか?
- ホーリーバジルの摘心方法と違い
- 摘心でよくある失敗とその原因
摘心のタイミングはいつが最適?

ベランダで育てるハーブ
バジルの収穫量を飛躍的に増やすためのキーポイントとなる作業が「摘心(てきしん)」です。この作業の効果を最大限に引き出すためには、適切なタイミングで行うことが何よりも重要になります。
摘心に最も適したタイミングは、バジルの苗が順調に成長し、草丈が20cm前後に達した頃です。この時期の株は、根がしっかりと張り、新しい脇芽を力強く伸ばすための十分な体力を蓄えています。
これより早い段階で摘心を行うと、まだ成長途中の株に過度なストレスを与えてしまい、かえって生育を妨げる原因になりかねません。逆に、タイミングが遅すぎて茎が木のように硬くなってしまうと、新しい芽の出方が悪くなることがあります。
草丈と合わせて、葉の数も良い指標になります。苗の一番下に生えている双葉(最初の2枚の葉)は数えず、その上から展開する本葉(ほんよう)が、6枚から8枚程度になった頃も、摘心を開始する絶好のタイミングです。節(茎から葉が出ている部分)の数で見る場合は、下から数えて3〜4節目を目安にすると良いでしょう。
作業は天候の良い日に行うのが鉄則
摘心は植物にとって一種の外科手術です。切り口から雑菌が侵入するリスクを最小限に抑え、傷口を素早く乾燥させるためにも、作業は空気が乾燥している晴れた日の午前中に行うのが理想的です。湿度が高い雨の日や、夜露が降りる夕方以降の作業は、病気の原因となる可能性があるため避けるのが賢明です。
この最初の摘心を適切なタイミングで行うことで、バジルの成長様式が「上へ伸びる」から「横へ広がる」へと切り替わります。これが、こんもりとした美しい樹形と、たくさんの収穫につながる第一歩となるのです。
バジルの摘心はどこを切るべきか

ベランダで育てるハーブ
摘心のタイミングをマスターしたら、次に最も重要なのが「切るべき正しい場所」を正確に理解することです。この位置をわずかに間違えるだけで、期待した効果が得られないばかりか、株にダメージを与えてしまうことさえあります。
結論から言うと、切るべき場所は「茎の頂点にある一番大きな葉のすぐ下で、その葉の付け根から左右に出ている小さな脇芽(わきめ)の真上」です。
バジルの茎を注意深く観察すると、葉が茎から出ている付け根の部分(葉腋)に、小さな新しい芽がY字を描くように控えているのが見つかります。この将来有望な脇芽を絶対に傷つけず、その5mm〜1cmほど上を清潔なハサミでカットするのが、正しい摘心の位置です。
植物には、頂点の芽(頂芽)が最も優先的に成長する「頂芽優勢(ちょうがゆうせい)」という性質があります。摘心はこの頂芽を取り除くことで頂芽優勢を打破し、それまで抑制されていた脇芽の成長を促す作業です。
正しく摘心が行われると、残された左右の脇芽が勢いよく伸び始め、1本だった茎が2本に分岐します。このプロセスを繰り返すことで、枝数が倍々に増え、収穫できる葉の枚数も劇的に増加していくのです。
絶対に切ってはいけない致命的なミス
摘心における最大の失敗は、成長の起点となる脇芽ごと切り取ってしまうことです。脇芽がなくなれば、そこから新しい茎が伸びることは二度とありません。カットする前には、指で葉をそっとめくるなどして、小さな脇芽が両側にきちんと存在することを必ず確認してください。
使用するハサミやカッターは、他の植物から病気を移さないためにも、使用前にライターの火で炙ったり、アルコールを含ませたティッシュで拭いたりして消毒することを強く推奨します。手で柔らかい先端を摘み取ることも可能ですが、その場合も清潔な手で行い、茎を潰してしまわないよう、爪を立てて綺麗に切り取ることが大切です。
摘心は何回くらいすればいいですか?

ベランダで育てるハーブ
「摘心は最初の1回だけ行えば良い」と誤解されがちですが、バジルの収穫量をシーズンを通して最大化するためには、成長に合わせて何度も繰り返し行うことが極めて重要です。
最初の摘心によって2本に分岐した茎がそれぞれ成長し、新たに本葉を6枚程度つけたら、それが2回目の摘心のサインです。その2本の茎の先端を、初回と全く同じ要領で、脇芽の上でカットします。これにより、枝の数は2本から4本へとさらに倍増します。
このサイクルをシーズンを通して継続することで、枝の数は幾何級数的に増えていきます。結果として、株は上へひょろ長く伸びるのではなく、枝葉が密に茂った、こんもりとした美しいブッシュ状の樹形に育ち、たくさんの柔らかい葉を効率よく収穫できるようになるのです。
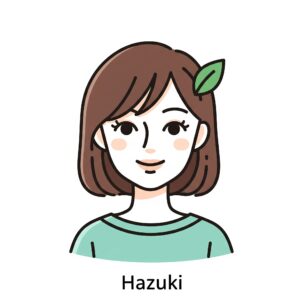
ただし、植物も生き物ですから、常に同じペースで成長するわけではありません。特に、根詰まりを起こしていたり、肥料が不足していたり、あるいは日本の夏の猛暑で株が疲弊している(夏バテしている)時には、過度な剪定はかえって株を弱らせる原因になります。
バジルの葉の色つや、ハリ、成長の勢いなどを日頃からよく観察し、植物のコンディションに合わせて摘心のペースを調整してあげることが、長くたくさんの収穫を楽しむための上級者の秘訣です。
ホーリーバジルの摘心方法と違い

ベランダで育てるハーブ
ハーブの王様とも称されるバジルには多種多様な品種が存在しますが、日本で特に人気があるのは、イタリア料理でおなじみの「スイートバジル」と、アーユルヴェーダで珍重される「ホーリーバジル(和名:カミメボウキ、別名:トゥルシー)」です。
基本的な摘心の方法、すなわち「脇芽の上でカットして枝数を増やし、収穫量を上げる」という原理は、どちらのバジルでも全く同じです。しかし、それぞれの品種が持つ特性や主な利用目的の違いから、ホーリーバジルを栽培する際には、より積極的かつ継続的な摘心が求められます。
| 比較項目 | スイートバジル | ホーリーバジル |
|---|---|---|
| 主な利用目的 | 料理の風味付け(ジェノベーゼ、カプレーゼなど)。一度に使う量は比較的少量。 | ハーブティー、健康・宗教目的。乾燥させて保存し、日常的に大量消費することが多い。 |
| 成長の特性 | 比較的柔らかく、草本性の性質が強い。 | 生育が非常に旺盛。茎が太くなりやすく、根本から木のように硬くなる「木質化」が早い。 |
| 開花の傾向 | 摘心をしないと夏以降に開花する。 | 非常に花をつけやすく、油断するとすぐに花穂が上がってくる。 |
これらの違いから、ホーリーバジルを育てる場合は、スイートバジル以上に「花を絶対に咲かせず、柔らかい葉と茎を常に収穫し続ける」という強い意識を持つことが重要です。
草丈がまだ低いうちから積極的に摘心を開始し、少しでも花穂が上がってきたら、葉を数枚つけて下の節から切り取るように管理します。これにより、株は常に新しい脇芽を伸ばすことにエネルギーを使い、質の良い葉を長期間にわたって収穫し続けることが可能になります。
摘心でよくある失敗とその原因

ベランダで育てるハーブ
バジルの収穫量を増やすための摘心は、非常に効果的なテクニックですが、いくつかのポイントを誤ると、期待とは裏腹に株を傷つけてしまうことがあります。ここでは、初心者が陥りがちな典型的な失敗例と、その原因を詳しく解説します。
最も多い失敗は、摘心後に株の元気がなくなったり、脇芽がうまく育たなかったりするケースです。これらの問題は、多くの場合、不適切な作業方法に起因します。
【要確認】摘心の主な失敗例とその対策
- 失敗:切る位置が低すぎる
原因と対策:早く大きくしたいという気持ちから、まだ小さい苗の根本に近い位置でバッサリと剪定してしまうと、光合成を行う葉が不足し、株が再生するためのエネルギーを作り出せずに枯れてしまいます。対策として、必ず株全体の半分以上の葉が残るように、切る高さを慎重に判断しましょう。 - 失敗:脇芽ごと切り取ってしまう
原因と対策:これは最も致命的なミスです。成長の起点である脇芽を一緒に切り取ると、その節からは二度と新しい茎は伸びません。対策は、カットする前に必ず左右の脇芽の存在を目で見て確認することです。焦らず、丁寧な作業を心がけましょう。 - 失敗:切り口から病気になる
原因と対策:植物の切り口は、人間でいう傷口と同じです。汚れたハサミを使うと、そこから雑菌が侵入し、茎が黒ずんで枯れ込む病気の原因となります。植物防疫の観点からも、使用する道具は事前にアルコールで消毒するか、火で軽く炙るなどして、常に清潔な状態を保つことが重要です。(参考:農林水産省「病害虫防除に関する情報」) - 失敗:不適切なタイミングでの作業
原因と対策:株が弱っている猛暑日や、湿度が高く雑菌が繁殖しやすい長雨の時期に摘心を行うと、株の回復が遅れたり、病気のリスクが高まったりします。対策は、植物の状態と天候を見極め、晴れた日の午前中に作業するという基本を徹底することです。
これらの失敗は、基本的なルールさえ守れば確実に防ぐことができます。植物への思いやりを持ち、一つ一つの作業を丁寧に行うことが、最終的に豊かな収穫へと繋がるのです。
よくある質問
F 摘心をまったくしないと、バジルはどうなりますか?
A 摘心をしないと、バジルは上へ一本の茎が伸びていき、やがて先端に花が咲きます。収穫できる葉の量は少なくなりますが、植物本来の姿や花を楽しむことができます。ただし、花が咲くと葉が硬くなり風味が落ちる傾向があるため注意が必要です。
F 摘心で切り取った葉や茎は食べられますか?
A はい、もちろんです。摘心で切り取った先端の柔らかい葉や茎は、香りが良く最も美味しい部分の一つです。捨てずに、そのままパスタやサラダなどの料理に新鮮なハーブとしてご活用ください。収穫と摘心を兼ねるのが効率的です。
F 収穫が始まった後も、肥料は与えたほうがいいですか?
A はい、必要です。バジルは生育旺盛で、葉を次々と出すために多くの養分を消費します。収穫期間中も、2週間に1回程度の液体肥料か、1ヶ月に1回の緩効性肥料を与えることで、葉の色つやが良くなり、長期間にわたって収穫を楽しむことができます。
F バジルの葉が黄色くなってきました。何が原因でしょうか?
A 葉が黄色くなる原因はいくつか考えられます。最も多いのは「肥料切れ」です。特に下の方の葉から黄色くなってきた場合は、追肥を試してみてください。その他、「水のやりすぎによる根腐れ」や「日照不足」も原因となります。土の状態や置き場所も一度確認してみることをお勧めします。
バジルを摘心しない栽培も魅力的
これまで摘心のテクニックとその重要性について詳しく解説してきましたが、最終的な結論として、バジルは摘心をしなくても十分に育てることができます。摘心を行うかどうかは、栽培の「目的」によって自由に決めるべきであり、どちらが正解ということはありません。
例えば、「たくさんの葉を収穫して、自家製ジェノベーゼソースを心ゆくまで楽しみたい」「こんもりと美しい形のハーブを育ててみたい」という方にとって、摘心は非常に有効で、ぜひ挑戦していただきたいテクニックです。一方で、「料理の彩りに数枚使えれば満足」「植物が自然に成長する姿を観察したい」「バジルの可憐な花を見てみたい」という方であれば、無理に摘心を行う必要は全くありません。
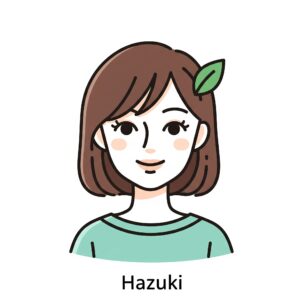
もちろん、摘心をしない場合は収穫できる葉の量が少なくなること、そして花が咲き始めると株全体のエネルギーが種子を作る方へ移行し、葉が硬くなり風味が落ちてくるという事実は理解しておく必要があります。しかし、それもまた植物の自然なライフサイクルの一部です。自分のライフスタイルやハーブとの関わり方に合わせて、最適な栽培方法を選択することが、家庭菜園を心から楽しむための最も大切な秘訣と言えるでしょう。
- バジルは摘心をしなくても元気に育てることが可能
- 収穫量は減るものの植物本来の自然な成長過程を楽しめる
- 摘心しない場合は可憐な白い花を観賞できる魅力がある
- 花はエディブルフラワーとしてサラダなどに利用できる
- 花が咲くと葉の風味が落ちて硬くなる点には注意が必要
- 栽培目的が少量利用や花の観賞なら摘心なしも素晴らしい選択肢
- 摘心はあくまで収穫量を増やすための園芸テクニックの一つ
- 茎が伸びすぎたと感じたらその時点で切り戻し剪定で対応できる
- 摘心しない場合でも日当たりや水やりといった基本的な管理は重要
- 自分の栽培スタイルや目的に合わせて摘心の有無を決めるのが最良
- 挿し木や水耕栽培を利用すれば苗を購入せずに気軽に株を増やせる
- スイートバジルとホーリーバジルでは摘心への意識が少し異なる
- 正しい摘心は適切なタイミングと切る場所の理解が鍵となる
- 摘心の失敗は基本的なルールを守れば防ぐことができる
- 収穫シーズンの終わりは気温の低下が大きなサイン
- 霜が降りる前に全ての葉を収穫し保存食などに活用する
- 家庭菜園は義務ではなく楽しみ、自分のペースで関わることが一番大切


